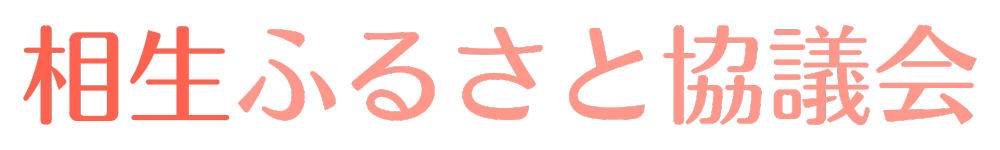○相生の歴史・沿革・概要
明治23年(1890年)坂元村・馬宿村・黒羽村・南野村・吉田村・川股村の6ケ村が 合併して「相生村」が誕生した。
相生村の各村には小学校があったが、明治25年(1892年)に統合され、南野小学校を相生尋常小学校とした。
昭和16年(1941年)には、相生国民学校となり、昭和22年 (1947年)には相生小学校となった。
昭和23年(1948年)には、相生中学校校舎が完成し、(それまでは相生小学校の一部 を利用していた)昭和47年に引田中学校と統合されるまで相生小学校運動場内にあった。
昭和30年(1955年)引田町・相生村・小海村が合併し、「引田町」となった。 合併により、相生村閉村式が相生小学校で行われた。
平成15年(2003年)に引田町・白鳥町・大内町の三町が合併し、「東かがわ市」が誕 生した。
平成23年(2011年)相生小学校閉校。(東かがわ市立引田小学校と統合。)